2017.09.15
#クリエイターズインタビュー No.52「傷物語VR」ヒットの理由 〜没入感を超える体験は「自分は何者か」という問いから生まれる〜
西尾維新氏原作「傷物語」全三部作の完結編ブルーレイ&DVDの発売を記念し、7月12日より無料配信されているPlayStation®VR向けコンテンツ「傷物語VR」。
開発にあたったソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア秋山賢成氏、アニプレックス淀明子氏、面白法人カヤック クリエイティブ・ディレクター天野清之が、その制作過程を振り返ります。
秋山賢成氏 ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア ソフトウェアビジネス部 次長
淀 明子氏 株式会社アニプレックス プロデューサー
天野 清之 面白法人カヤック クリエイティブ・ディレクター

―「傷物語VR」の反響はいかがでしたか?
- 秋山賢成氏
- いい意味で、あり得ないくらいの反響でした。ダウンロード数の伸びの速さもすごかったですし、ポジティブなコメントをたくさんいただきました。一人あたりの起動回数もとても多く、何度も繰り返し見てくださっているようなんです。
- 劇場版「傷物語」完結編のブルーレイ&DVD発売と同時に無料配信したのですが、これまで「傷物語」を見たことがなかった方から、PS VRで経験して「DVDを買いました」とコメントをいただいたのも印象的でした。作品のPRとしても大成功だったのかなと。
「没入感を超える体験」を実現するためには「自分が何者か」「なぜここにいるのか」という物語が必要
―制作ではどのようなことを工夫されましたか?
- 秋山
- 僕からお伝えしていたのは、どう実在感を高めるかという点です。「自分は何者か」「なぜここにいるのか」ということを、きちんとユーザーに理解してもらうことが、VRコンテンツではすごく重要だというお話をしました。
- 天野清之
- 秋山さんと話した「自分は何者か」というキーワードで頭の中が整理されまして、思わず「超わかりました!!」と声を出してしまったくらいです。
- 「傷物語」のダイジェスト版で編集した映像に対して、VR空間に演出を入れていく構成で進めていたのですが、秋山さんの言葉を聞いて考え直しました。視聴映像をバトルシーン中心に再編集して、テンポの良いものにすることで視聴の時間を減らしました。
- コンテンツの体験時間が10分程度と決まっていたので、映像を短くし、キスショットとコミュニケーションをとりながらユーザーが目の前にあるリモコンを手に取って再生ボタンを押すと、プロジェクタに映像が映し出される。
- このステップを挟むことで、「自分は何者か」「なぜここにいるのか」ということを、ユーザーの方にすっと理解してもらえるようにしました。

VRは体感するメディア 「気持ちよさ」の感覚が重要
- 淀明子氏
- アニメーションをつくるロジックでは、なかなかできない構成なんですよね。そもそも暦がキスショットと一緒に映画を見る設定なのに、映像の中にキスショットが出てくるって、辻褄が合わないじゃないですか(笑)。
- でも、辻褄を優先して考えることよりも、あの世界の中で、どれだけ映像を楽しむかということの方が大事なんだと、体験した時は不思議と違和感がありませんでした。違和感をまったく感じさせないから、観てくださった方が、これをきっかけにDVDを買ってくださったりということにつながったのかなと思います。
- 天野
- おっしゃる通りですね。無茶なつくりだとわかっているのですが、理解をしていただきましてありがとうございます(笑)。

- 淀
- 天野さんの運動神経がいいのか、感覚が鋭いのか(笑)、辻褄が合わないところがあっても違和感がなくて、見ていて気持ちいいんですよね。これが正解なんだなと感性が受け入れてしまう。VRって、やっぱり体感するメディアだから、頭で考えるより感覚の方が大事だと感じました。
- 天野
- 最後のシーン(霧のシーンから光が飛ばされる演出)も、見ていて気持ちいいと思うんです。ただ、あのシーンが最初に出てきて、同じような演出のオンパレードになったら、「面白い」という感覚は、たぶん1分も続かないです。ユーザーがVRに対して求めているVRっぽい演出ってあるんですけれど、それだけだとつまんなくなっちゃう。
- 淀
- 飽きてしまった瞬間、没入感が失われてしまいますよね。
没入感を超える実在感 ”Sence of presence”がVRには必要
- 秋山
- 我々は「実在感」といっているんです。没入感を超える実在感、Sence of presenceを生み出すためには、自分がその世界に入ったというのではなくて、“無自覚にその世界にいるという感覚”が重要だと思います。そのためには準備や演出のワンステップが大事なんです。いきなり作品世界に入ってしまうと、わーって楽しんで、あー面白かったね、というアトラクションで終わってしまうので。
- 実在感って、すぐ壊れてしまうもので、たとえばVR酔いや、作中で動いているのにリアルの体が動いていない感覚不一致などが起きると、一瞬で現実に戻ってしまう。そうなると、そのVRコンテンツ体験はいいものにならないんです。
- センシティブで難しいんですけど、それをいかにテクニカルに解決をしていくかということと、演出でうまくカバーしていくかということが、VRコンテンツをつくる上で重要だと思っています。
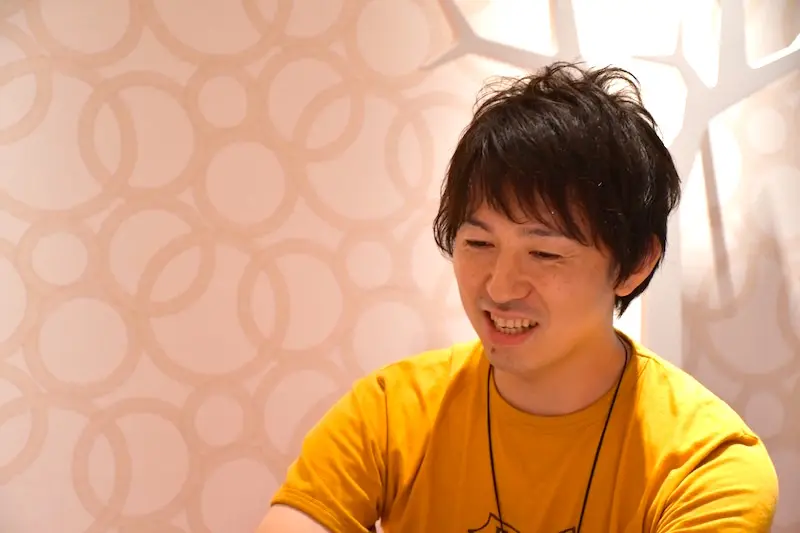
- 天野
- VR酔いの一番の原因って、感覚不一致だと思うんです。VRの世界で移動する時、気持ち悪くなることがあるじゃないですか。でも、自分が何をしているかということを理解するだけで、その酔いが軽減される。
- 一度、実験してみたことがあるんですが、同じ空を飛ぶにしても、いきなり飛ぶ設定と、自分の目線でコントロールして飛ぶ設定では、自分でコントロールする方が、気持ち悪くならないんですよ。
―その検証結果は「傷物語VR」にどう活かされているのでしょうか?
- 天野
- まず全体設計ですね。先ほどの話のように、「自分が何者であるか」という視点を確立したこと。「自分が何者か」という視点を明確にすることは、すなわちVR世界における感覚の一致につながります。それが秋山さんのアドバイスであり、もともとの構成案を変更した理由でもあるし、「傷物語VR」が成功した理由のひとつでもあるのかなと。
- 秋山
- 今回の制作過程では、社内の会議室で、僕がヘッドセットをつけて、横にいる天野さんに修正点を伝え、酔いや感覚不一致につながる違和感をひとつひとつ直していきました。たとえば教室の壁の模様。もともとのアニメーションの素材ではポリゴンで描かれていたのを、テクスチャーに変更してもらいました。リアルすぎてVRコンテンツとしては違和感を感じるので。。
- 天野
- モワレによるVR酔いの可能性や、首を振った時の残像を軽減する方法など、すごく勉強になりました。

二次元のキャラクターに三次元の命を吹き込む VR×アニメーションの表現の可能性
―アニメ「傷物語」の再現性で苦労されたことはありますか?
- 天野
- キャラクターの質感設定については、ずいぶん悩みました。イラストに輪郭をつけた立体物のような表現だとちょっと合わなくて。最終的には、少しだけ半立体を意識して、立体物の質感を残しつつも、立体物のような明確な影の落ち方はしないものにしました。
- VRの中で、アニメのキャラクターの造形をどう設計するかというのは、まだ正解はないし、いろいろな可能性があると思うんです。
- 最終的にこれでいこうと決めた方法は、完全にファン目線ですね。自分が作品のファンとして見た時に、キスショットがかわいいと思えるかどうか。これです。
- 淀
- 「傷物語」のファンの方たちが、3Dになったキスショットと出会ったらきっとこんな感じなんだろうなというのを、天野さん自身がファン目線で(笑)、キャラクターとしてつくり上げてくださったのがよかったんだろうなと思います。
VRは世界の拡張を体感として記憶に留められる装置
- 天野
- ちなみに、よく見ないとスルーしてしまう特殊な演出も実は入れているんです。何人くらい気づいているかな。
- 淀
- えっ、どこだろう。
- 天野
- 画面が割れるシーンで、ずっとキスショットを見ているとびっくりしますよ。あそこは、描画している画面を割ってるんです。なのでユーザーがみてる視点で割れます。VRって結局、平面モニターの連続じゃないですか。そこを逆手にとってみました。空間が割れてその後ろに別の世界が登場するのってVRじゃないとできない演出ですからめちゃめちゃ面白いと考えてます。こういう見せ方って掘り甲斐があるし体験として、未到達の領域に行けると思います。
- 秋山
- 現実世界では物理的に難しい演出が、VRの世界だとできちゃうんですよね。
たとえばビームライトのような直線光を出す時、リアルで表現しようとすると、すごく難しい。ところがCG空間だと、きれいな直線光がすぐつくれちゃう。物理現象とか現実的な制約、予算感の制約とかが、全部可能になるから、そこが面白い。
- 淀
- でも人って、もともと自然に、そういう風に段階を経て、物事を見ていると思うんですよね。たとえばミレーの「落穂拾い」の絵をみて、すごいなと感じて、それをもっと近くで見たいと思う。近づくとこういう技術で描かれているんだな、そしてこの時代ってどんなだったんだろう、季節は寒い時期なのかなって想像する。VRって、その思考を現実で再現できるというか、近づいて鑑賞して、テクスチャーを見て、気がついたらその世界に入ってしまうみたいな体験ができるわけですよね。
- VRを使っていくと、世界が拡張されていくことを、実際の体験として感じることができる。アニメーションは、実写と違って、限られた中の表現だからできることと、できないことがあると思うんです。でもVRを使うと、そこをより広げて、しかも体感として記憶に留めることができる。すごい装置だなって思いますね。

インタラクションを増やすよりも、映像が語りかけてくることによって実在感が増す
- 秋山
- VRというのは手段ですよね。「こういう世界をつくりたい」という頭の中のイメージをぶつけるキャンバスがVR。VRでないととできないことをしなきゃという発想からつくると、頭でっかちになっちゃって、もったいない。
- バーチャル空間でものを持ったり、投げたり、ぶつけたりするのって、それだけですごく楽しいんですよ。でも、そういうインタラクションを増やすことだけが解じゃないと思うんです。
- 今回の「傷物語」で大きな知見を得たのは、いわゆるインタラクションを増やすほど実在感が高まるのではなく、逆に世界というか、映像が自分に干渉してくることによって、実在感が高まるということでした。
- 自分から動かなくても、受動的にエンターテインメントを享受したいという層の方が、母数としてはおそらく多い。今回、そういうコメントもたくさんいただいたことが、大きな気づきでした。
- 淀
- フィクションの世界に入るには、展示会やアトラクションのようなイベントで体験するか、自分の想像力しかなかったわけですよね。VRの出現によって、その中間が生まれたように思います。
いまはVR創世記、ファミコン黎明期のようなゲームをつくりたい
―最後にお一言ずつお願いします。
- 淀
- 今回の「傷物語VR」を体験してみて、もしかしたら将来映画館がなくなるかもとさえ思いました。でも、劇場でみんなで一緒に見る感覚というのはずっと残るのかなと。感動を共有する場とVR、それが共存できる世界がきたらいいなと思います。私たちもそのために、いろいろなコンテンツをつくっていきたいです。
- 秋山
- 声優の神谷浩史さんに「傷物語VR」を体験していただいた時のコメントが印象的でした。VRプロジェクションマッピングの出現によって、クリエーターが作品を届けやすい世界がつくれる、とおっしゃって。
- テレビで見る時って早送りしたり、ながら見になって、つくり手が一番伝えたいところを見逃される可能性があるけれど、映画館ではそういうことがない。VRも同じように、つくり手の伝えたいことを余さず伝えられる場所になると。今回のプロジェクトを通して、そういう可能性が今後出てくるんじゃないかと思っています。
- 天野
- クリエーターやエンジニアの立場からは、どうしてもVRの先端技術を目指したくなりますが、現状の制約の中で、どうやってイマーシブな体験をつくるのかが面白いと感じています。PS VRというのは、すごく面白いコンテンツをつくれるデバイスですから。
- 今はVR黎明期だと思うんです。約30数年前に家庭用テレビゲーム機が生まれた時と同じですよね。制約された条件の中で、ミニマムな技術で普遍的なクリエイティブがたくさん生み出されたわけじゃないですか。そういうものを、VRの世界でつくりたいと思っています。

バックナンバー#クリエイターズインタビュー

誰も期待していなかったゲームが1000万DLに化けた理由 ー「Number Merge Run」逆転の舞台裏
No.98
誰も期待していなかったゲームが1000万DLに化けた理由 ー「Number Merge Run」逆転の舞台裏
2023年にリリースされた「Number Merge Run」。初速のダウンロード数も及第点で、長い間「目立たないタイトル」となっていました。社内でも「期待されていなかった」このゲームが2年の時...
2026.01.30

ブラックサンダーをルアーに!?釣具メーカーDUOとカヤックが挑んだ開発の舞台裏
No.97
ブラックサンダーをルアーに!?釣具メーカーDUOとカヤックが挑んだ開発の舞台裏
行動食としてのブラックサンダーに、新しい体験価値を持たせたい。
そんな依頼から始まった企画は、気付けば「本当に釣れる”ルアー”を作ろう」という大胆な挑戦に進化していった。
釣具メーカー・DUO(...
2025.12.11

4ヶ月で1000万DL突破!インドネシア出身のゲームクリエイターがカヤックで培った「失敗の筋肉」とは
No.96
4ヶ月で1000万DL突破!インドネシア出身のゲームクリエイターがカヤックで培った「失敗の筋肉」とは
インドネシアでゲームボーイに魅せられた少年が、海を越えて鎌倉の開発現場に立ち、リリースからわずか4ヶ月で1000万ダウンロードを達成──。 「Grapple Hook Hero」を生み出したのは...
2025.12.10

ハイカジで1000万ダウンロードのヒット連発!AI時代を生き抜く「技術で面白くする」ゲームづくりとは
No.95
ハイカジで1000万ダウンロードのヒット連発!AI時代を生き抜く「技術で面白くする」ゲームづくりとは
ハイパーカジュアルゲーム「パペットマン・オフロード」「Shuriken Cut」の2タイトルが、それぞれ累計1000万ダウンロードを突破。生み出したのは、大手ゲーム会社で家庭用タイトルなどを...
2025.11.04

未経験からゲーム事業部へ!1000万DLを達成した「手を動かし続ける」開発哲学
No.94
未経験からゲーム事業部へ!1000万DLを達成した「手を動かし続ける」開発哲学
1000万ダウンロードを記録したハイパーカジュアルゲーム「Draw Block Gladiator」。このタイトルを企画・開発したのは、Webエンジニアとして入社し、ゲーム開発経験ゼロから挑戦し...
2025.10.03
 Facebookページ
Facebookページ 公式X
公式X 代表柳澤のX
代表柳澤のX